レビュー
- 第9回 – 2024年
- 第8回 – 2023年
- 第7回 – 2022年
- 第6回 – 2021年
- 第5回 – 2020年
- 第4回 – 2019年
- 第3回 – 2018年
- 第2回 – 2017年
- 第1回 – 2016年
- 第0回 – 2015年
審査員講評 田辺剛 氏
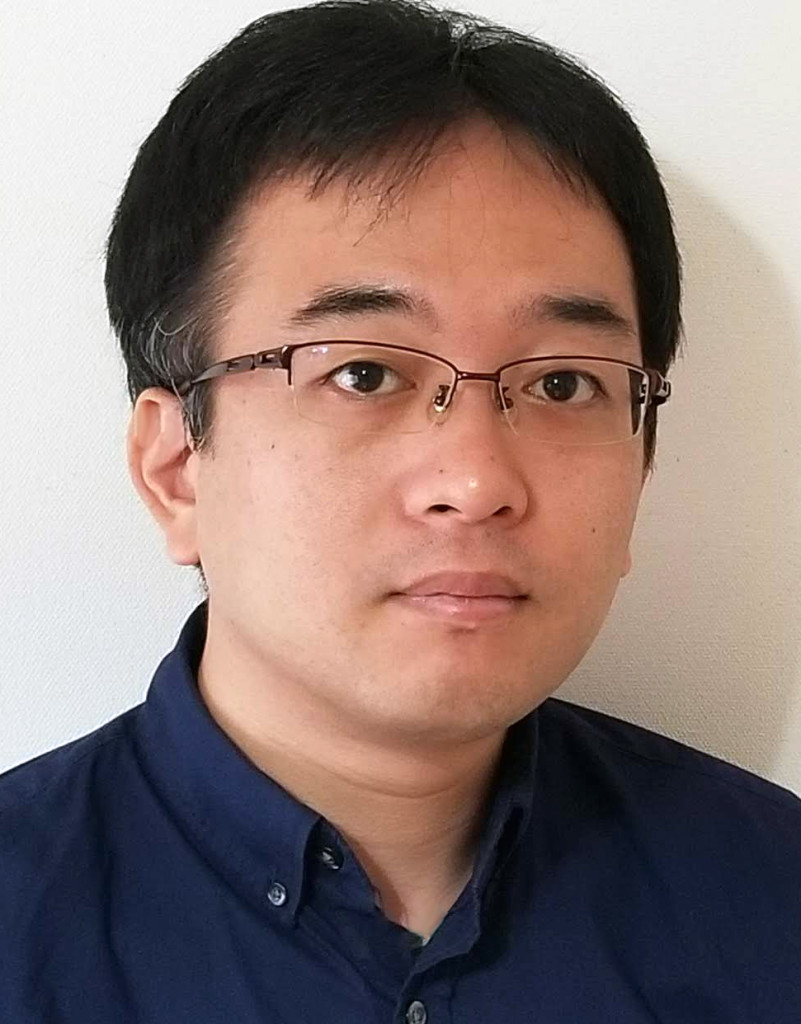
総評
選考会の場で授賞にふさわしいものとしてわたしが推したのは、ゆり子。の『あ、東京』と楽一楽座の『LIVED』だった。また、でいどり。の『夕暮れの公園、静寂を忘れて。』を次点として挙げた。他の審査員お二人ともが『LIVED』を挙げられたこともそうだけど、『夕暮れ……』をお二人とも(次点としてすら)挙げておられないことに驚いた。わたしとして悔いが残るのは『あ、東京』の魅力をその場でうまく説明できなかったことだ。容易に語らせないこと自体が魅力でもあるのだけれど、観客賞の結果を聞いてなお悔しさが募った。もちろん『LIVED』の授賞に異存はない。
戯曲(テキスト)ではなく上演の審査だということは重々に承知しているが、テキストのことは棚に上げて上演を見るということは実際にはできない。テキストの詰めの甘さや瑕疵は上演の出来に直結するし今回拝見した作品でもうまくいっていない上演の原因をたどればテキストの問題になることがほとんどだ。そうしたなかで『LIVED』のしっかりしたテキストと充実した上演(演出)のバランスの良さはわたし個人の趣味は棚に上げても認めるところだ。一方、『あ、東京』はテキストとしても上演(演出)としてもむしろ傷だらけなのだけど他にはない魅力があった。そういう作品が忘れらてはいけないという思いから推したのだった。『夕暮れ……』は他のお二人の出方を見ながらと思ったのだけどなかなか議論の俎上に乗せることができなかった。
以下に講評めいたものを書いてはいるけれど、懇親会や打ち上げの席でそれ以上のことを各団体と、しかもすべての団体とお話しできたのは嬉しかった。賞にも漏れて選評会でだいたい感想を聞いたらばそれ以上はという人もいてよさそうなものの参加団体の方から話を聞きに来てくれた。その熱意に打たれた。
またどこかの劇場で再会できればと願っています。どうぞ創作を続けてください。
Aブロック
fooork『ユニアデス』
一輪車がただそれだけではなく別の何かとして扱われることで作品の核心を象徴する装置になるはずなのだが、と期待したのだけれど、物語のスピーディーな展開のなかで結局ほとんど「一輪車」のまま置き去りにされていた。それは舞台の目的が事故に遭った女性の顛末を語って聞かせることに収斂したことの代償だ。はじめは、作品の動機はきっと違ったにちがいない。けれどもなぜこの作品に一輪車が必要なのかという問いが作り手の側でだんだんと失われていったのではないだろうか。
stereotype『感染性ピエロ』
これはコントだと言われたがわたしはまったく笑わなかったので、であれば失敗に終わったのだなと席を立とうとしたときだ。ふと引っかかったのはコントなんだから笑えよと客席に投げられた幕切れの台詞だった。もしかすると作り手はそれまでに披露したコントで客は笑わないことを前提にしていたのか。わたしが笑わなかったのではない、そもそも彼らは笑わすまいとしていたのではないか。だから笑えよと言ったのだ。そうでなければ言うべき台詞は「ありがとう」になるはずだろう。笑わすまいとしたならばメタ構造を持つことになるこの作品は果たしてその先になにを目がけていたのだろうか、などとその引っかかりに結構な時間をわたしは費やすことになった。けれども笑わすまいとしたにしてもわたし以外には笑う人もいたこと、そもそも笑えなくなっているのは何にでも意味を汲み取ろうとするからだという仮説が乱暴で(たいていの観客はある時には器用に意味を汲み取ることをやめて「お笑い」を楽しんでいる) さまざまな角度から考えてもそのメタ構造は機能していない。かといって、きちんと時間を守って集合した生徒らに未着の者のことを怒る教師の愚かさのようなものが舞台にあるわけでもない。いったいどういうことなのか。結局、審査会などでこの作品は観客を笑わせようとする素朴なコントであるらしいとわたしは理解し、わたしの結論は冒頭のもので問題がなかった。
劇団しろちゃん『ネクタイとスイカ割り』
例えば「みんな違ってみんないい」という一節があるがその寛容さが同調圧力の道具として使われれば、みなは違わなければならないその差異を主張せよという風潮を作ることにもなりうる、そんな現代社会への皮肉であったり、正論や正義がかえって人々を苦しめることにもなるその両義性への問いをこの作品は孕んでいる。ただ実際に上演されたのは、仲間と行く旅行の目的地について二者択一の選択をなかなかできないでいる個人の日常の物語だった。それは演じる俳優らの等身大の舞台作品として評価を得ることもあるだろう、しかしわたしはこの作品が持つ問いを遠くに追いやったことをもったいないと感じた。そもそも何かしらの選択を迫られる風景は昨日も今日も明日もわたしたちは生活のなかで目の当たりにし、また自身もその渦中にいるわけで、わざわざ劇場に出向いて再確認するほどのことではない。確かに他の審査員が指摘するように、舞台の構成や演出、俳優の演技が写実性の強いその物語の上演に過不足なく働いていたことに異論はないけれども、それだけの上演力がある集団ならばなおのこともっと遠いところに焦点を当てられたのではないかと思われる。
Bブロック
楽一楽座『LIVED』
薬なしでは眠れない男が安眠を得るまでの間に見る幻は、彼が愛する音楽の、彼自身が歌うライブコンサートにある。舞台の観客はそのライブの聴衆でもありその二重の立場で彼の歴史に付き合うことになるだろう。この作品が観客に感情移入を強いるような独白劇に陥らなかったのは彼の背後にもう一人の男性がずっといたからだ。その男性はライブのDJであり主人公を少し高い場所から見守る役でもある。主人公がどれだけヒートアップしてもその背後には沈黙する男がいるという構図は観客の劇への感情移入を阻ませる。そのおかげで観客は傍観者として主人公の人生に立ち会うことが可能になる。観客(聴衆)とDJと、さらに何体もの人形に男は囲まれている。その人形は彼の歴史の節目であり彼を孤独にする装置だ。そうした場所で俳優は一人きりで右往左往し睡眠薬をあおる男の人生を滑稽に演じた。歌という幻によって聴衆たる観客の前で披露される男の人生と、演じられる物語によって出現する男の人生という幻が混在してとてもユニークな劇空間が立ち現れていた。一見すると哀れな男を騒々しく描くだけの作品のようでいてその劇の構成は複雑でいくつもの要素が有機的につながっている。思いつきだけでは成し得ない。この作品とそれを実現させられる力は無視できないものだった。
ゆり子。『あ、東京』
例えばそれを「時代の波」と言う人もいるだろう。「同調圧力」「すべての真ん中」あるいは「モラトリアムへの感傷」「未来への憧れの裏返し」「社会への不安」など言いようはさまざまにある。この作品ではそれを「東京」と名付けた。すでによく知られたことばだ。首都であり日本最大の都市の名であり、そこで生まれた文化や技術、政治、経済も含まれる。けれどもそれがいわく言いがたいものの名として付けられた途端に、元々の意味やそこから連想されるイメージは裂け始める。東京はそれ自体が生物ではないし、それ自体が若者のなりたい対象でもない。そして秋の足音のようにわたしたちの街にはやってこない。けれどもそれは「東京」と名付けられた。当然に誰もがそれの意味するところを探るだろう。そのようにして既知の意味や連想されるイメージに裂け目を作りそこへ観客の想像を誘うことによっていわく言いがたいものに触れさせようとする。この作品は冒険心の強い言語実験だ。果たして既知の「東京」が裂けていくのを目の当たりにする観客は当惑しつつ作品が表現しようとするいわく言いがたいものに触れる。触れたとてそれが何であるかは理解できない。理解できるわけがない。それはまったく未知の「東京」なのだから。
そこには外から迫り来る脅威への不安と父を失った喪失感のはざまでなんとか自己を保ちたくて、すべてと一つになりたいと渇望する女がいる。その母は男と遊びまわり、ついには女の恋人とも関係があることが分かる。そんな彼女とその周辺を描く劇の側面は「東京」のモチーフと比べて目につきやすいし観る側の焦点がそこにあたるのは自然だろう。それだけであれば陳腐な家族劇でしかない。しかしこの作品の魅力はそうした女の近況と遠くから迫る「東京」のはざまを舞台にしたことだ。わたしたちの生をとりまく得体の知れない何かについて想像を仕向けること。20歳そこそこの若き者らの飛躍する想像と創作を羨ましく思った。
一方で、「東京」と名付けてみた曰く言い難いものにたどり着こうとする試みは破綻とまでは言わないまでも未整理で、あるいは創作者ら自身が既知の「東京」のイメージから抜け出せずに取り込まれていた部分もあるだろう(東京の風景を映像で出すのはわたしにとって蛇足だった)。それでも暗中模索する舞台にわたしは好奇心と想像を強く掻き立てられたし今回拝見したなかでもっとも興奮させられた作品だった。
Cブロック
ミチタ カコ『夏の続きは終わらない休み、雨の音は聞こえている』
演者のつま先から指の先までぬかりなく演出家の目が行き届いている、ダンスとまでは言わないまでもそのパフォーマンス(便宜上このように呼ぶ)は強い印象が残った。ある女性の中にある複数の声という設定をきっかけにその振り付けは生まれたのかと推察するが、その着想と実際の表現に興味をもった。ただ、二人の女性の隠された真実が明かされるという謎解きに収斂する物語とその俳優らのパフォーマンスは結局乖離するように思われて、実際に語りが増すところでは俳優らは動かなくもなる。戯曲が語る物語とは別の物語をパフォーマンスは紡ぐべきだったのではないか。結果として戯曲に従属することになるのだけれど、戯曲と対峙するべきではなかったのか。戯曲としては確かに詩的な響きはあっものの物語はありきたりな謎解きで、ぬかりなく目が行き届くパフォーマンスに寄り添わせるのではなく追いつかせない密度があればと思った。戯曲とパフォーマンスの関係がもっと緊張したものであれば作品としてさらに豊かになるのではと思う。
でいどり。『夕暮れの公園、静寂を忘れて。』
無差別に殺した子どものなかに自分の息子がいたのだと告げ知らされる男と、自分の息子をかつての夫であり父である男に殺された女と、その二人が再会したときにこそ生まれることばがあるはずだ。何も言いようがないかもしれない、沈黙にしかならないかもしれないそのことばをもっと聞きたかった。殺すまであるいは殺されるまでの過程の話もいいけれど、ことばが失われそうなときにこそあの疲れ果てた俳優らがさらに何を語るのか観たかった。残念ながら劇としてはそのころにはことばはほとんど尽くされていて、復讐の添え物になっていた。女を処刑してはならなかった。子を失い、子を殺したかつての夫の死も背負い、あの女優に舞台で語らせるべきだった。ことばが無ければ沈黙でいい。舞台に一人きり長い沈黙のなかにいればいいではないか。たとえ語る主体が失われてもことばは残るということが演劇の核心だという私見から、この作品においては行為や存在にことばが従属しているのが不満だった。悔しかった。
劇団バッカスの水族館『結婚したら両目を瞑れ』
確かに夫へのストレスはあるのかもしれないが、それは目を瞑(つむ)ってしのげるほどのことなのか、妻自ら目を潰すほどではないのか、登場人物にとって状況がどれだけ切実なものなのかそれほどのことでもないのではないかという疑念が最後まで拭えなかった。母に味方する年頃の娘はどうしてそんな父と会話できるのか、処世訓の域を越えないことしか言わない宗教団体の教義はいったいなんなのか、どうして舞台空間の中央を空っぽにするような配置なのか、疑問が絶えなかった。不意に星空を家族みんなが仲良く見る場面の挿入や、見る/見ないという境界線がやがて崩れて見えているのに見えないという事態に進むことなど引きつけられる点もあったけれど、劇作家の理屈が先行しすぎて物語の世界の構築が雑になされているように思われた。