レビュー
- 第9回 – 2024年
- 第8回 – 2023年
- 第7回 – 2022年
- 第6回 – 2021年
- 第5回 – 2020年
- 第4回 – 2019年
- 第3回 – 2018年
- 第2回 – 2017年
- 第1回 – 2016年
- 第0回 – 2015年
観劇レポート 蜜柑さん
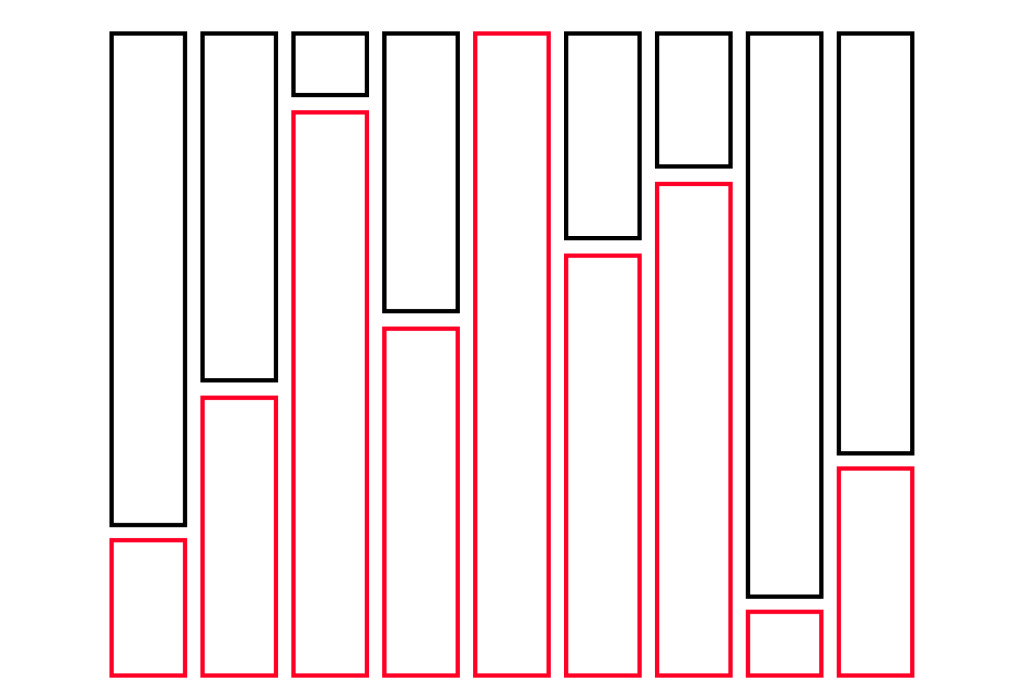
第2回全国学生演劇祭の演目を観劇し、舞台の模様を広く伝える”劇評/レビュー”を書いていただく方を募集し6名の方に担当していただきました。
蜜柑さん
観劇専門・観劇歴3年目の20代女性
Aブロック
- 劇団宴夢
四国を影の薄い存在をぞんざいに扱っていると、四国が独立帝国を作ってしまうかもしれないというコメディでした。
北海道から遥々京都までやって来て、四国の宣伝というのがずいぶんハチャメチャだなぁと思いました。もっと対等に扱って!私たちだってやるときゃやる!という叫びは、まさに四国県民の、いやいや日本のなかで都会と比べられ、影が薄いと揶揄される県民全員の心の叫びでもあるのでしょう。演者のルックスや体型を、プロトタイプ的な性格特性とリンクさせていたので、すっと頭に入りやすかったように思います。
- 劇団西一風
セットアップ・道具類は一番大がかりでした。タイトルのピントフは霧吹きのことでした。ピントフを使って流れ作業をする工場が舞台。ただただ流れ作業。ひたすら流れ作業をしながら地域事業の話をする所長と従業員。所長はコストを気にする癖して、新しいものは勧められるがままに購入。購入品のひとつであるルンバ(?)が始終舞台で動く様はひたすらシュールでした。こんなにシュールな演劇を三本立てでやっているというのだから驚きです。所長の購入品に労働を搾取されようがされまいが、こんな会社が本当にあったらすぐ潰れてるだろうなと思いながら見てました。
- 南山大学演劇部
最愛の妻を亡くした悲しみゆえに、父は自分にたいして暴力を振るう毎日。ある日父は主人公のなかに妻の面影を見つけ、愛情の対象として見始める。そんな父は主人公にとって支配者でしかなかった。自由を求める主人公はついに父を殺める。
結局、愛してくれない父を殺める方法はなんでも良かったんだと思う。現実世界では有り得ないテクノブレイクという殺めかたは、最後まで自分を認めてくれなかった父、妻のことで頭が一杯で、主人公のなかにある妻の面影を抱く父を報復の意を込めて殺害するのに手頃だったというだけで。それにしても、壊れたテレビのような効果音(突如鳴る&かなり大きい)、赤い照明はかなり怖かったです。
- 劇団カマセナイ
3年前に自殺をしてしまったちぃちゃんと、ちぃちゃんを忘れることのできない小山と高橋というシンプルな構成。
ちぃちゃんのことを引きずっているということは共通していても、いつまでもメソメソ泣いてばかりで、泣き止みたいと願う小山と、悲しいはずなのにひとつも泣けなくて、生前に交わした「ちぃちゃんが死んでしまったら泣く」という約束を果たせずにいる高橋が対比して描かれていました。
高橋との会話のなかで、一ヶ月後には学校の机には花瓶が置かれることになる、とさらっと口にしていたちいちゃん。自殺の理由は語られていませんでしたが、彼女は親友にも相談できずに、一人心のなかに一体どんな闇を抱えていたのでしょうか。また、自殺に踏み切ってはいなくても、その瀬戸際で揺れる「ちぃちゃん」は、日本に何れくらいいるのでしょうか。
台詞はひとつも噛むことなく、台詞の抑揚や発声等々の基本的な技術力は、さすが大阪の学生演劇祭を勝ち抜いただけあるなと感じました。
- 劇団なかゆび
共演予定だった相方が当日バックレたので自分一人で45分をしのがなくてはならなくなった。という内容は、事実ではなく演出だろうとは思われました。が、「それでは始めます」と言ったきり、誰も舞台に出てこずに5分10分ただ照明に照らされた小道具だけが目の前にあり続ける光景は「もしかしてガチなの?」と思わされてしまいました。それでも誰一人文句を言わずただ待ち続ける観客は偏見かもしれませんが「日本人だな、、」と思っていました(大人しく見てた私も立派な日本人)。理不尽なことにも文句を口には出さずにいる態度は、当事者からすれば「折り合いを付けている」こと。そうやって理不尽を感受する「観客」は、舞台に上がる彼にとって至極つまらないという。
よくある「考えさせられる演劇」ではありませんでした。
パンフレットを見ると、「劇場の<外>への訴えを常に持つ」の文字。今回もご多分に漏れずの設定でした。
- 一寸先はパルプンテ
男女という枠組みに悩む10歳の子供2人。日本国籍はあってもハーフで海外在住期間が長いということで日本代表と認めてもらえない女性。富が富を生み、貧困が貧困を生む教育格差…。差別・区別といった「境界」をオムニバス形式で取り上げた演目でした。境界は人為的なものにもにも関わらず、普段から無意識に大多数が認め、行動の基準にしている。 そんな境界に疑問を投じるというわかりやすい内容でした。境界をただ周囲が認めているから、文化だからといった理由で無批判に受け入れるのではなく、時々でいいから立ち止まって考えてほしい。そういったメッセージがわかりやすく伝わりました。
- シラカン
三人+一羽の演者による演目でした。喋らないでいてくれる机が恋人だというヒカリと、「自分には目もくれずにヒカリのことが好きだというソウタ」が好きだというレンコ。ちょっと変わった愛情をもつ二人の女の子と一途な男の子一人、という印象でした。が、話が進むにつれてカオスとしか形容できない展開になりました。他者から見れば「変わっている」「常軌を逸している」考え・言動・愛であっても、当の本人にとってはそれが唯一無二の正しい世界。演劇のなかではあからさまに描かれていましたが、他者に理解してもらえようが貰えまいが構わないという自分の世界は、現実にいきる私たちも多少は持ち合わせているのではないでしょうか。
年配の方には付いていきづらい内容であったかもしれません。しかし、そんな「若者ならでは」こそが、学生演劇祭の実行委員長さんが挨拶で述べていた、粗削りながらも「既成概念を打ち破る」ことに繋がっていくのではないかと感じました。
- 劇団マシカク
男性三人によるコメディでした。
演者が三人、そして過去や未来を行ったりすることもなく、ということでとてもわかりやすい内容でした。
スマ×スマ、ハリポタ、ドラゴンボール、コナンなど私たちが生活していて実際に関わる世界と上手く絡めていて面白かったです。
私は普段あまりテレビを見ないので、もっとそちらに普段から接している方々はより面白おかしく見れたのではないでしょうか。
男性三人が秘密にしていたこと、最後の一人は御曹司だったということ?
デビュー講演で演劇祭出場を決め、そしてその演劇祭が解散公演ということでしたが、高い演技力や飾らない真っ直ぐな脚本ゆえに惜しまれます。
- 岡山大学演劇部
人々の人生が巡りゆく様が、短い時間にぎゅっと詰め込まれていました。観客自身、生まれてから死ぬまでの人生を俯瞰的に見ることを迫られる内容でした。
例えこれと言って取り上げることがなくても、語り継がれることがなくても、一生を生きぬくということ。迷いながら、自分の不甲斐なさに落ち込みながらそれでも自分が自分として生きていくこと。
大地球という規模で見ると小さい世界かも知れないけれど、自分にとってはそれがいまの自分に見えるすべて。そんな世界でもがきつつも、人生を歩んでいくのだろう…と、演劇終了後には思わず「生きること」について思いを馳せてしまいました。演技を魅せつつも観客も上手く世界観へ誘う演目でした。机や扉・ベルやベンチなどの静物さえも人で賄っていたのが目新しく面白かったです。
- 幻灯劇場
若い、の一言につきます。性、生演奏のギター、バンドに狂う人々、力で押し切ろうとするところ、ミュージカル・ダンス・演劇を45分に詰め込んでいるところ…全てが若いと感じさせられました。
抽象的・非現実的な世界を多く扱っていたのであまり自分に引き付けて考えることができず、共感出来る点は少なかったです。そういった意味で、不快に思われるかも知れませんが、発表会を見ている気分になりました。雑多なものを一纏めにして並べて、見せる・見せつける演目に感じたということです。
「既成概念を打ち破る」というよりはプロフェッショナルを目指している最中のアマチュアであり、いささか独り善がりになってしまっているという印象を受けました。