レビュー
- 第9回 – 2024年
- 第8回 – 2023年
- 第7回 – 2022年
- 第6回 – 2021年
- 第5回 – 2020年
- 第4回 – 2019年
- 第3回 – 2018年
- 第2回 – 2017年
- 第1回 – 2016年
- 第0回 – 2015年
観劇レポート 平井寛人さん
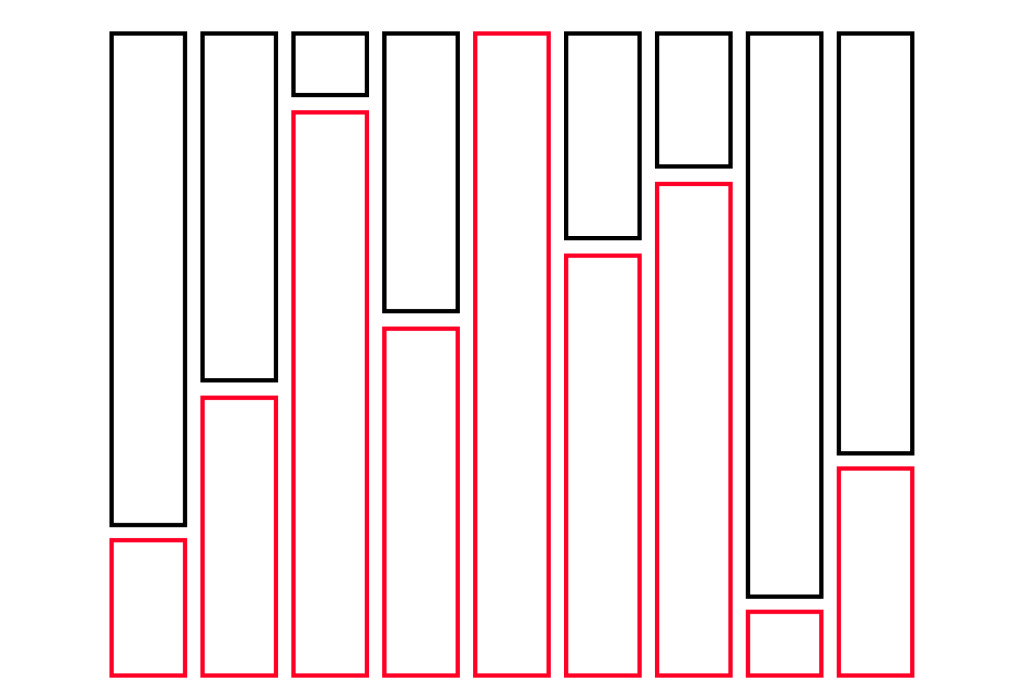
第2回全国学生演劇祭の演目を観劇し、舞台の模様を広く伝える”劇評/レビュー”を書いていただく方を募集し6名の方に担当していただきました。
平井寛人さん
FUKAIPRODUCE羽衣 作家部在籍中。
全国学生演劇祭に、期待を寄せています。演劇界が新たな人々により動き出していく中で、その予兆を察するために優れた劇団が集まっているよう予感します。
私自身20歳の学生として、本委員会の夢ある表明に同意します。この興奮の中で僭越ながら、滾って私自身寄与できるようなレポートを届けたく存じております。全団体へ期待します。
Aブロック
- 劇団宴夢『大四国帝国』
「腹が座ってバランス感覚も良い」
絶妙なバランス感覚によって、演じる事とキャラクターを優れた距離感で再現している。ときにはシニカルな視点を用いながらも、キャラクターの持つ愛らしさを損ねず、媚びているわけでもない。
どの役者の演技も良かった。特に香川県を担当していた方の気のふれたくらいのストイックらしさには、見ていて癖になる部分があった。バカはするが徹底的なバカにはならず、冷静な秘書が常に角にいるのもそうなのかもしれないが部分的に冷めた目線を忘れていない、やり取りの中の人物配置に極めて好印象を覚えた。
伝わるところまで伝えられれば良いやというような、潔さが良い。中にはくどくなっているセリフやユーモラスな言動の箇所もあったが、伝わるかどうか分からないが、もしもそれらをくだらなさを隠すための保険として防衛本能的に入れてしまっていたのなら、必要なかったのかもしれない。より一層、堂々と出来れば格のような恰好がついただろうと感じた。それらは折角のテンポを妨げているものでもあるようにも私には感じられ、観劇中に更なる洗練さを欲しがってしまっていた。
どの部分においても、全力というか、諦めという事をハナから放棄しているようなパワフルさが、私に対して高い好感ポイントを促している。うどんのゴリ押しを聞くと、うどんがある意味ファッションのようになって私はうどんと触れ合いたくなった。そういう舞台だった、と思う。この舞台においては皮肉くさくないのが、観客を付き合わせる要因として機能していた。
- 劇団西一風『ピントフ™』
「自由自在に見えるような、何も無いような」
在るのか無いのか分からない緊張感が常に漂っている。その隙間を、結局リアルで本気なのか非リアルで冗談なのか明確にならないうちに、言葉がぬるりと分け入ってきて客席に際立って届く。
これらは何かを縫うように私たち観客の知りえないところで進行していき、やがて事件を予感させるので、次から次へと起こるイベントに気を引かれ続けた。
不用心なようでいて確かに計算的な描画が舞台上でなされていると私は感じた。不発したようなギャグもどこまでも自然で、「ここはこうあるべきだ」という作家らしい、哲学のような、諸所への批評的な狙いの数々が、むしろ私たちに距離を取らせながらも自由にシーンを探索させた。
重要なのは、それでいて作者の顔・哲学が自由奔放に反映されつつも、観客が考察の余地を持ち続けられる点である。セリフの一つ々々は思えばわざとらしい、悪戯心らしい思惑を感じるところだが、それによって破壊されない世界の強度がすでに築かれていた。
すると作家は思うがままにギャグを挟め、つまり直接的な観客とのやり取りを行いながらキャラクターたちの生活を、鮮色的に一列に描いていた。何をおろそかにするでもなく、『ピントフ™』は終始観客との探り合いに結実している。面白かった。
もはや玩具として機能していたような、舞台装置の嘘か本当か分からない飄々とした具合は、もはやイタズラ的で恨めしい。
ただ壮大な何かを立ち上げる過剰さが不足しているよう感じた。もう一展開最後にパーティが必要だったのかもしれないし、交響曲的な作品として若々しい挑戦へと一歩が必要だったのかもしれない。もっとも、高尚さでも理不尽さでもない、ディスコミュニケーションをふんだんに用いた作風が心地良かった。
- 南山大学演劇部「HI-SECO」企画『絶頂終劇で完全犯罪』
「大胆なワード選択か浅薄なパワー」
コントロールが上手くつけば、より高いエネルギーをもたらすと感じた。可哀想なキャラクターだから同情されて気を引けると考えているのなら、多くの場合で間違いである。話を聞かせようとする工夫に事欠いていないようには感じられず、説教臭さだけがあると変な剥き出しになってしまう。その生々しさは、最初の部分では好ましく、後にいくに連れて仕様もなくなっていった。
後半の部分で、折角のエネルギーが良く分からない、閉鎖的な型に閉じ籠ってしまって勿体がない。才気はそれなりに発揮されようとある舞台であるふうには予感された。そうした未然の予感らしさがあまりに顕在されていて、私は観劇中随時心もとなく感じていた。
下品な言葉といったものを刃物のように扱うだけでなく、相手をくどき落とすような、低い格式から見た切実な本物として演出する事が出来たなら、『絶頂終劇で完全犯罪』は更なる愛おしさを持たれる、あるいは拒絶される見応えある作品になったのではないかとぼんやり思う。
また、大きな声を出していても存在感が稀薄で、役者が観客から下に見られてしまうような状態になってしまうのはどうしてだろうか。鼻についてしまうし、こちらから応えられない。『絶頂終劇で完全犯罪』に限られた話ではないが、私たちの大きな課題であると思った。
- 劇団カマセナイ『ナインティーン・コスプレーション』
「気色わるさと静かな祈り」
決して愚弄ではないのだけど、45分程度の『ナインティーン・コスプレーション』の中で、チーちゃん(の容姿のどうこうは関係なく)の額に「ブス」と書いていて欲しい。
それは思い付きにしても、この劇からはそういったレベルでの不穏さがかもされていた。不穏な舞台は本来客席に働きかける力が強く、前半部分特に気色に優れない。
多くの、説明がいらないコスプレーション、コンプレックスは確かに胸を打って有用に働いていた。それらは演者と観客の病の共有体験のようで、どこまでも鮮烈だった。優れたセンスとコントロール能力を感じた。
ただ長い。不用意に長いと軽くなる。やり取りがただ二人の惰性的で、くたびれたような依存し合ったようになった時に、対策をこうじていないと溺れてしまう。溺れた演技に客席から無視されない何かが必要だったのではないかと私は感じた。
この孤高らしさにネタバレは必要だったのだろうか。ネタバレて以降、感傷的なものに現代人は恐らく浸ってくれないのではないか。慣れられてしまっている。何者かを静かに想い、祈る表現姿勢には強く共感する。ただ、自分が良いと思って始めた味わいには最後まで責任を持つべきであるとも感じる。
自分が好きだと思ったところから移り変わって、纏めるため、温くや甘くなってしまうのでは作家の真面目な性格を怯えて示しているふうにしか出ない。嫌われる勇気を推す。
また、役者が二人とも良かった。もっと自分勝手にやればより良いよう感じる。面白かった。
Bブロック
- 劇団なかゆび『45分間』
「ノイズミュージックとしての言語通話」
セリフ、発される足音といったものと、思考の距離感について考えさせられた。定点的な二点のマイク、その間でなされる言葉や物体の行き来が、ラグとなって新たなバグのような思考の効果を発揮せんとあるようだった。
後ろで一列に走る木の装置とその上で機能を得たり放棄されたりするギターやボールがよく端的に働いている。(話している)内容については下品で、不快に軽薄ではないにせよそれ自体は取るに足らないものなのだが、テクストから思考が独立する可能性に、多くの面から寄与しているよう私には思えた。視覚的、ワード選択から、果敢な挑戦が感じられた。この時、どこまでも、ノイズミュージック的である。雑音でしかない舞台上から発される音を、極めてシニカルに扱っている。
それから役者の胆力には感嘆する。ただ言葉選びについて、生まれつつあるはずの美に対してあまりに無頓着であるようなのに私は非難する。どう言おうと伝わらない人には伝わらないが、『45分間』にしては格好良くないのだ。メロディのないロックは何も言葉を届けない。あと、最初から出ずっぱりだった役者の前髪が気に入らなかった。
ノイズミュージックとしての言語通話は確かにありうると感じる。エジソンが「結果が
真摯な過程によって生まれた時、実験はそのものとして成功である」みたいな事を言っていたと思うが、そうした点で私は支持をしたい舞台だった。
- 一寸先はパルプンテ『境界』
「足りない層」
おどけた態度での鋭角的な主張は心地良く、新たな立場を選び取ろうとする心強い若々しさがあって私は爽快に感じた。役者の表意能力にも若干の才を感じた。ただし顔や表情にパワーやエネルギーが生じるように、前髪で生まれてしまう陰のところにも確かな力があるのだというところへの意識が必要だ。隙は多い舞台だ。そういうところでなお、真面目な事を真面目な顔で堅苦しくない態度から真面目に伝えようと、無自覚への警鐘に展開を繋げた点について、私は些かの共感をした。
遠慮をまったくしない、暴虐無尽な展開が魅力だと感じた。危機感から完全に逃れて展開を運ぼうとする飄々さには心強く思え、境界が立ち上がって見えた。ただし、あの線の「使いよう」はあまりに無尽蔵であった。それを絞りきれていない、幼い無自覚さが感じられ、どう言おうと伝わらない人には伝わらないが、つまらない層だけつままれ面白い層だけが靄として心中に残ったような、ドラマとは別の不完全感が私には否めない。
体格というのも才能であるが、小さな体にしてはパワー不足で、あらゆるものが小さい。照明の軽さがそれを際立たせていて、それに対する抗いがないのが私には僅かに不快だった。足りないものが主張を試みようと、「ソーワット?」それ自体でしかないのではないか。多くの要素において、根本的に足りていないいけない破綻を感じた。
- シラカン『永遠とわとは』
「新たな可能性への飛翔」
負けじと打つ将棋師のような、圧倒的なバランス感覚の良さと大胆さに脱帽する。疑いようのない才能であると思う。こうなっているとタイトルも良い。舞台上に演出家が理想として描く雰囲気、イメージ、エネルギーが巧妙かつ自我も過剰であるかのように独特に築かれつつあり、展開が進むにつれ確かに飲み込まれゆくような感覚を覚えた。
舞台美術、照明、脚本、演出、音響、役者、どれをとっても何かの独立した可能性に対してそれぞれの横暴ではない解釈で歩み寄り合っている。隙がなく、勇猛果敢であり嫉妬さえ覚える(私などがおこがましいが)。面白かった。照明が綺麗。
最初に流れている音楽が、導入部で不安であるというのも分かるが幾らかくどくあざとい。役者が望遠鏡を持って舞台をはける時に望遠鏡を持つヴィジュアルとして気の抜けるのが早い。最初の部分の女優のセリフが聞こえづらく、完璧を目指すならばこうした「不快さ」はあだになる。最後の部分で最も顕著なように、舞台上の装置や物が止め処なく増えていくようなところ、それらが構図としてあまりに整理されているところなどから、頭の中の世界を再構築しようとする作風を感じた。この作風において、表現の枷になる表現上のあだが散見させられる。細かい部分に対する、作家としての更なる一アイデンティティが感じられると、最高そのものにより近づくように感じた。
一口にいって、一つの客席からの無関心を打破するような舞台であった。真摯に感心する。新たな可能性への飛翔を演劇界に対して新たに感じ、彼彼女たちの新たな可能性への個人としての飛翔を改めて期待する。
Cブロック
- 劇団マシカク『自憂空間』
「逃避の跡に残る、単色の連続と生々しさ」
単色の球が多く転がり、舞台上を満たすと演じられる事柄はまったく非現実的な物事になる。役者もそれぞれが衣装によって単色を担っており、性格や役割に対して単純明快な差別化を行使しているようだ。
不用意な言葉や安易なギャグを入れ込む事で、人は舞台でおこなわれている事をどうにも信頼出来なくなっていく。すると演技という奇行をしている役者を浮かび上がらせてしまう。引用されたようなギャグの数々や唐突なパロディーーその時、役者自身の生活感が生々しく押し出されてくる。共同住居での生活感というより役者の諸々が見えてくる。
役者が生々しく見えてくると、ここで私(に限らず客席にいた人々)はそれらを愛らしく見るかどうかの選択を迫られる。こうした事態に対し、『自憂空間』の役者は巧みに努めていたよう私には感じられた。言葉遣いを自分の身に引きつけ、等身大の姿で演じようとする強さには心惹かれた。
ただ、それぞれが「俺が俺が」と出ている以上、意識を及ばせていないとコミュニケーションが上手くいっていなく見えたも事実だ。お互いが相手の目を認識するようになって、そうしてて事を運ぼうとすればより良かったのではないか。
こうした事を思っている時でも、舞台上に多く散乱する単色のさまを見ていると、こうした事でさえ繋がりを持った大仰な事ではないのかもしれないと思わされた。現実逃避をしているニートたちの、嫌だ嫌だという悪小僧じみた思いつきの連続だけが、ここでは再現されていたのかもしれない。しかし細部への自覚が足りているようには思えず、まだ欲しがいがある作品だと感じた。
- 岡山大学演劇部『山田次郎物語』
「捲られる日々と優し過ぎる説明」
言葉も丁寧が過ぎると無礼になる。相手への気遣いが行き届いていない状態である。何か詩的な内容を伝えようとする時にも、あまりに優し過ぎる説明では子供騙しじみた演目になってしまう。
『山田次郎物語』は一つ一つ思いを持って日にちを綴っていこうとする繊細さは持ち合わせていながらも、一方で自己本位な話ぶりをしている側面を持っていた。媚びが付着しており、結果不親切で、相手の理解を省みられていない、そうした危うさを私は感じた。
すっきりとした型に隙なく丁寧に嵌め込まれていながらも、話の展開にダレが生じていた矛盾に私は靄を感じてならなかった。
はっきりとした喋り方、明確な動き、等々どれもが入念に検討され、広く染み渡っている。そうした好ましい表現がなされていた。
山田次郎という人物への姿勢も良い。日を繰る中で温もりと共にある生涯を伝えようと役者が総員で役割を分担し、時間と手間を捧げている。時間を横断しようとする野心もあったと見受けられた。
分担しようというところに、歯車意識を私は覚えてしまったのかもしれない。玩具が起動し、ショートカットをおこなえずに律儀にすべてを立ち上げる感じは、現代の人々とは距離を置いてしまう。いつまでも演劇それ自体が面白く、慣れられていないものではありえない。若干の古めかしい表現というのも、ここでは無批判に認められた。
もっとも、面白くないわけではなかった。捲られる日々と、それを精一杯誠意を持って届けようとする優しさには心打たれた。
止まる時間がもっと効能に意識的にあると、良いのかもしれないと感じた。
- 幻灯劇場『DADA』
「高いテクニックと、溺れる陰」
学生演劇がプロの演劇より背が低いというのなら、全団体において最も背を伸ばして観客に何かを届けようと、クオリティを高めようと心していたのは『DADA』であっただろう。
良い言い方を選べば、客を巻き込むショーチックである。
美的なシーン、状況の作り方にはいたく共感する部分がある。
人を誘い込むセンスに疑いようはないだろう。ただ、目につくだけというだけでは底が見えるので、底の計算を放棄したところから始まる根底の規律があるとさらなる飛躍があるのではないかと感じた。
コンサート、ライブ、ショート形式、それらにはパワーがある。ただしそれらを利用するだけ利用して、「どうそのパワーを助長し人を引きつけるか」という工夫が無ければそれは思いつきでしかない。意地悪く言えばこの舞台は思いつきの連続であり、テクニックを陳列した抜け目なさが御輿を担いでいると思った。
私は、巻き込まれず、そもそもプロと比べたら十分な用意が出来ない舞台でもありながら、既存のプロの舞台と比べられるところしか『DADA』からは感じられず、不満ではあった。
相性の問題ではなくここで否定できないパワーを省みた時、しかしそれらはコンサートっぽさの部分のみであるように感じられ、何かを切り裂くような鮮烈さやそれを補ってトランスさせるドラマとの一体感はほぼなかった。
思いつきと、何かを発掘しようとして出てきたものは決定的に異なる。『DADA』およびに幻灯劇場の野心に求められるのは、幻灯劇場に対しては推測でしかないが、何か可能性を発掘しようとする荒々しいまでのエネルギーではないか。すると『DADA』はパワー不足甚だしかった。
面白くはあった。ただ、ドラマ性にしても「ソーワット?」なところが否めない。幽霊が溺れる陰が、人の陰でしかないなら、お遊戯らしさが浮かび上がってしまうと感じた。