レビュー
- 第9回 – 2024年
- 第8回 – 2023年
- 第7回 – 2022年
- 第6回 – 2021年
- 第5回 – 2020年
- 第4回 – 2019年
- 第3回 – 2018年
- 第2回 – 2017年
- 第1回 – 2016年
- 第0回 – 2015年
観劇レポート 一人静さん
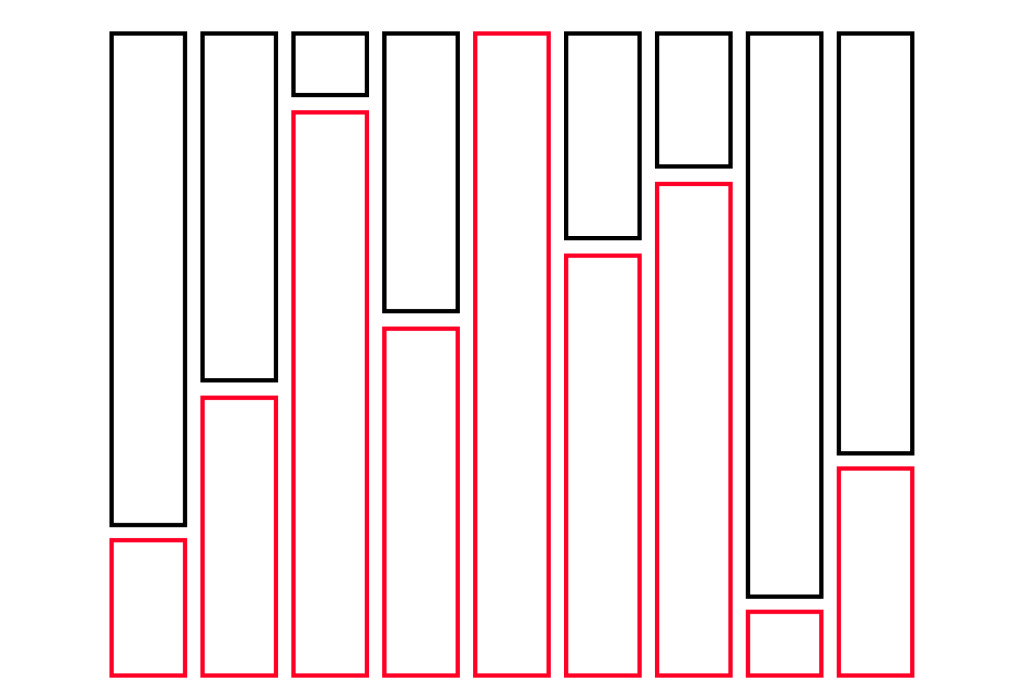
第2回全国学生演劇祭の演目を観劇し、舞台の模様を広く伝える”劇評/レビュー”を書いていただく方を募集し6名の方に担当していただきました。
一人静さん
その昔、劇団ACTという劇団に所属し脚本と演出を担当していました。
好きなものは映画と海外ドラマ。今食べたいものはチョコクッキーです。
Aブロック
- 劇団宴夢「大四国帝国」
最初の驚きは北海道の団体が四国をネタにしているということでした。もしかすると団体の中に四国出身の方がおられたのかもしれませんね。そのような楽しみも全国学生演劇祭の楽しみであり、あるいはこの公演の楽しみの1つだったのかもしれません。
国を擬人化した作品と言えばヘタリアが記憶に新しいですが、今作では四国4県の擬人化に加え、それぞれの県に新たに特性(徳島がヘタレ、神奈川がうどん屋、愛媛がギャル、高知がオタク)が追加されていました。そうした中で鑑賞していてどうしても疑問になったのが、最初の設定である県の擬人化とその後のキャラ付けがうまく機能しているのか?ということでした。結果から言うと、うどん役の女性(彼女は素晴らしかったですね)以外は擬人化という部分で台詞以外で設定が生かし切れていないことが少し残念でした。
四国が独立し、どういうわけかアメリカが侵略してくる。そこからそれぞれの県の特色を生かして解決策を模索するまで盛り上がった勢いが、いざ「アメリカとの決戦」という最大の見せ場ではあっさり片付けられたのは見たかった最大の見せ場がスキップされてしまったように感じました。設定の突飛さに対して、結末はどこか宿命論的である意味「リアル」と言えなくもないですが(四国が独立するということが現実的であるかどうかは別として)広げた想像力を急速に萎めているように感じました。
しかしながらそれぞれの役者は愛嬌があり、稽古も重ねられたのだと感じます。北海道の団体が四国のネタをするということも含めて軽快なコメディだと感じました。
- 劇団西一風「ピントフ™」
同名の公演を2度(2015年の西一風の公演、2016年の京都学生演劇祭)見ているので再再演と思いながらで観劇していました。初演時には今作で見られたような「面白さ」(コンセプトのようなもの)に必ずしも焦点が当たっていたわけではなかったように思います。しかし上演を重ねる上でこの作品の持つ「面白さ」に作家が自覚的になり、それを確信犯的にやっている。そのことが今回の公演の面白さであり、他の団体との明らかな意識の違いであったと思います。
今作では作家の視線は前面に押し出されて主調されることはありません。言い換えるなら大声で主題や社会的な問題を提起することがないということでもあります。ただ我々は工場にやってきたある新人の初日を通して、工場らしき一室で行われる「ピントフ」という得体のしれない(しかも後に登場する「パンタモス」との違いなど全く分からない)装置を経緯に繰り返される「消費的イリュージョン」を垣間見ることになります。
舞台前方に設置された運動性を持った舞台機構や、背後の絵画、樹木、上手のデスクなど空間への配慮がなされていた点も良かったと思います。また一室にずらっと一列に並ぶ役者が(いい意味で)全員パッとしない。交わされる台詞もどこか上の空で、会話も相互に興味を持って行っているようには到底思えない。また後半にかけて登場する機器(ルンバ、加湿器など)に比べ工場で働いている労働者の作業が単調で、並列に鑑賞できると言った視線を投げかけてくる、その様々なレイヤーの背後にある「既視感」が今作最大の魅力だと思います。この作品から我々はそのどこか既視感を持つ情景に様々な思いを巡らせ、そしてどこまでも想像を膨らませることができるでしょう。舞台上の狭い空間をより広い視野にいざなうその手付きは見事だったと感じます。また再再演の今回の上演においては中国人労働者の女性と主人公が交わす以下の台詞が個人的には白眉だったように思います。
「退屈ですか?」「ハイ」
―西一風と、そのメンバーに賛辞を贈りたいと思います。
- 南山大学演劇部「HI-SECO」企画「絶頂終劇で完全犯罪」
名古屋代表と言うことで、今年もコメディの作品を上演されるのだろうかと予想していたらいい意味で期待を裏切られる作風であり、名古屋演劇界の底知れなさを感じます。以前、前述した西一風が名古屋学生演劇祭で公演したこともあったので地域間の交流がこうした作品を(もし)生み出すきっかけになっていたのだとすれば演劇祭はとてもいい交流になっているのではないでしょうか?と、余計なことを思ったりしました。
さて、そのような前置きは横に置き、今作がどうであったかと言うと、正直あまり感心出来るものではないように感じました。白黒の衣装、ぐるぐる回る演出、裁判、仮面、神、罰、性、近親相姦など(何故か)学生演劇で良く持ち上げられるモチーフではないかと思います。そこで考えるのはそれ自体のテーマを選ぶことが悪いことではなく、どうしてそのテーマを扱うことにしたのか、また何を面白いと感じているのか、公演として何がやりたいのか、ということです。哲学も学生演劇では散見される主題の1つですが、それを自分のやりたいことに繋げているのか、それとも哲学という主題自体を面白く思い、それを扱っているかどうかでは話が違うと思います。それは穿った捉え方をすれば「弁証法って面白いじゃないですか?ほら、これ弁証法だよ?弁証法?」というような無邪気な姿勢ではありながら、聞き手からすれば「いや、弁証法?知ってるけどそれが何?」なんて、もし最初のデートで言われたりなんかしたらそこには冷たい沈黙が訪れる惨事になりかねないのではないでしょうか。もしかするとこのような場合においては「弁証法ってのがあるんだけど、そういえば昨日さ…」と自分なりの文脈や物語に繋げて話していれば相手の関心を引き出し、幸せなひと時を過ごすことができたかもしれません。
前置きは長くなりましたが、今回の公演ではそのような「それが何?」という場面が多かったです。冒頭で提示されたテクノブレイクの突飛さから始まり、白い服の男のモノローグも近親相姦のワードの破壊力の前で高い拒絶感を感じ、距離感を感じます。もしかすれば、その拒絶感や忌避の感情を喚起させるものだったのかもしれませんが、どうにも提示される言葉がそれ以上の意味を持って届いてこないので、言葉の羅列で終わっているように思いました。また母の失踪を契機に父が子に母の面影を感じ近親相姦に及ぶ。最終的には子が母に変装(もしくは同一化)し、父を(間接的に)殺害する一連の話のオチが「どうして愛してくれなかったのお母さん!」という絶叫で終わることは果たして良かったのでしょうか?このような凄惨な結末を迎える原因となった母への同一化をしてまで最後まで母への無条件の愛を求める、彼の異常なまでの母への執着とは何だったのでしょうか?
こうした疑問や道筋の中で作家がやりたかったこととはなにか?と考えた時に「意味などない」という主張は正解のように見えて、存外に作家や演じ手の隠された欲望を意図せず露見させているのではないかと思います。脚本を書き、上演するというプロセスの中で一種「自明」の元とされ、そのまま観客の前に提示されたものの中には作り手の世界観や無意識の欲望が(本人の意思とは関係なく)垣間見える瞬間があります。もしかすれば今作もそうしたものが垣間見えていたのではないでしょうか。しかし、それが事実であるか本当のところは誰にもわかりません。ただ、多くの人にとってそうした欲望を自分の意図しないところで暴露させられるのは大変不愉快なことだということは変わらないと思います。それが事実であれ、そうでないにしろ「自分すらも気が付いていない欲望」を他人に観察されるのは苦痛です。そうして理解された気になられ、消費されるのは耐え難い感情ではないでしょうか?
ではそうした中で作り手はどのように描いていけばいいのでしょうか。もしかすればそれはある意味で、迷宮を作るような作業ではないでしょうか。物語という高い壁を持った迷宮を建設し、その最奥に謎を巧妙に隠す。迷路にはそれを解きたいという欲望と、絶対に隠しておきたいという二つの欲望が交錯しています。そしてそのような迷宮は往々にして非常に魅力的です。今回の作品もそうした迷宮を作り上げることによって魅力的に人を誘う作品になったのではないでしょうか。
- 劇団カマセナイ「ナインティーン・コスプレ―ション」
小山/ちいちゃんを同じ女優が演じつつ、ちいちゃんを巡る死の真相を巡る前半のサスペンスに比べ、その後にほぼ永遠とも思えるほど続く感傷のシーンには正直、辟易したと言うしかありません。鑑賞していた体感としてはサスペンス:感傷=8:2ぐらいでしょうか。3年前に死んでしまった同級生の死というテーマは確かに人生に暗い影を投げかける重要な事件だと思います。そこに疑いの余地はありません。しかし今回の公演では2人の登場人物があまりにも「ちいちゃんの死」の感傷に浸ることによって寧ろその事件に対しての入り込めなさを形成し、疎外感を感じさせ、観客に冷めた視点を持たせずにはいられませんでした。前半で直ぐに回収されてしまう黄色の点字ブロックなどは示唆的でとても有用な舞台美術だったと思いますし、前半のサスペンス部分を増やし構成を調整していれば、もしかすれば「ちいちゃんの死」という題材はもっと違った印象に感じられたかもしれません。
話は少し変わって、今回の公演でのこのような長い観賞において劇作家はいったい何をやりたくて、何を面白いと思っているのだろうかと良く考えます。今回の公演においては「亡くなった死者を悼む」ということがその第一義的な主題だったのでしょうか?私には単純に(たとえこれが作家の身近に実際に起こった事件だったとしても)「私のことを忘れないで」という願望に支えられた、作家の自己保存的な願望に基づいているのではないか?と邪推してしまいます。これは本当に嫌な言い方で、コイツは何を言っているのだという感じだとは思いますが、今作においてはそのような作家の姿勢が剝き出しで舞台上にさらされていました。それはある意味で、自身の大切な記憶すらも簡単に消費されてしまう様な状態になっていたのではないでしょうか。劇中にも描かれていたように人の死は突然に、そしてほとんどが理解できないものだと推察します。大切な思い出を消費させない為にも、記憶に対して自分がその記憶とどのように付き合っていくのか?一時的な悲しみに囚われるのではなく、創作という形で記憶を昇華させる、そのような視点が含まれた時、個人的な感傷の記憶も人の心を動かすことになるのではないでしょうか?
Bブロック
- 劇団なかゆび「45分間」
何も面白いとは思いませんでした。それが全てであり、この劇(と便宜上は呼ぶことにしましょう)を「見て」それ以上の意味を汲み取る気もほとんど起こりません。眠たいと思いましたし、実際に寝ていました。個人的な営みとして睡眠はとても有意義であり、このような長時間の観劇体験において眠りはとても魅力的であり、事実、快楽的です。
その短い睡眠時間の中で(事実、眠ることが許されている時間は45分間しかない)私は夢を見ました。夢の中で私はとても幸せな甘美な情景を回想していました。美しい情景です。それは形容のし難い、一種観念的な美の様なものであったのかもしれません。それは静かな海のようでありながら、同時に深い森を思わせていました。
- 一寸先はパルプンテ「境界」
いくつかの不幸な物語が語られ、最後には「シュプレヒコール」「革命」と言った言葉が用いられる。経済的・人種的・社会的・宗教的等、様々な不和に対しての是正の眼差しが提示される内容でした。それは見上げるべき主張であり、疑いようのない高潔な姿勢だと思います。しかしながら鑑賞していて主張に対して万人が同調できるか、共感できるかと考えると個人的にそうではないと思いました。それは主張に対する反発ではなく、方向性を伴った作品の特質なのではないかと思います。ある一方の方向に向けて作られた作品はある意味プロバガンダの様な作用を持つ場合があります。今作の個別の主張の正しさとは別に、鑑賞後に出口が見えてしまうことはそれが社会的に容認すべき事態だとしても、そこに乗り込めない人をかえって阻害してしまうことになるのではないでしょうか?
劇中に語られるエピソードは強烈です。気分を害する人もいたでしょうし、今回の様な結末を持たなければヤバイと言う意識を(もしかしたら)作り手が持つこともあり得るでしょう。また観客においてもこのようなラストがあるからこそ、それまでのエピソードは(感情的に)チャラにされ、救済されていると思うかもしれません。
しかしながら、そのような凄惨なエピソードだけを見せつけられるだけ見せつけられ、一切の救済もなく終演を迎えた場合においても、結末の主張と同じような感覚を(逆説的ですが)観客はより「自発的」に見出だすことができたのではないでしょうか。それは圧倒的な社会的な悪を目の前に、それまで関心のなかった対象に良心が痛む、という風に。
- シラカン「永遠とわとは」
抜群に素晴らしかったです。例えるならまるでドッグフードのクッキーにチョコレートコーティングした物をバレンタインに用意して「食べて!食べて!」と無邪気に勧めてきそうな、そんな印象を持ちました。
人間なので好みもあるとは思いますが、こうした作品を観ると、正直「面白さ」の様なものをイチイチ順序立てて人に説明するよりも「面白さ」をポケットの中にしまい込み、いざ自分が面白い話をするときにこっそりと取り出して、さも自分が考えた物のように丁寧に偽装したくなります。ですが面白いと感じた人間の1人として、ささやかながら簡潔にその魅力を紹介していきます。まず、個人的にこれは凄いと思ったのが、その「力んでなさ」だと思います。無理しているところはほとんど感じられず、無理のないセリフがポンポンと繰り広げられます。これは並大抵にできることではありません。これには確かな語感や、期待を裏切る言葉選びのセンスの様なものが必要とされているでしょう。しかしながら今作からは無理をして台詞を言っていると言った印象がほとんどありません。しかもほとんどマジックの様なレベルで。そのことが大変に素晴らしい。
話の構造や、主題、こういうことをすると面白くなるかなというような期待感は確かにありますが、それを差し引いても45分間3人のラブコメ(+鳥と机)で集中してみることのできる作品は稀でしょう。また役者がそれぞれ大変魅力的で自律的に舞台に存在し得ていることが強烈でした。あまり多くの言葉を投げかけると、それを巧妙に吸収されそうな薄暗さを感じるのでそろそろ結びにしたいと思います。
――今後の活動に大いに期待を寄せると伴に、最大限の賛辞を贈りたいと思います。
Cブロック
- 劇団マシカク「自憂空間」
『こんな話をしないでくれよ、面白さはそこじゃないだろ?』という声が聞こえてきそうですが、やはり最後に同性愛的な主題を出した意味が謎です。それを「面白いから」以上の解釈で捉えることができません。別にそれをすることは自由ですし、そうした内容が面白いと感じているのも個人の自由です。ただそれは言い換えるなら「同性愛的なギャグをすればウけると思うし、実際に自分も面白いと感じている」と意図せずアピールしているのともあまり変わりません。怒っているわけではなく「なるほどそういうことが面白いのか」という、それだけの話であり、人によってはそれが全てです。
多用されるアニメや特撮の文脈を用いて45分間の劇が成立させ「分かりやすさ」を武器に展開される公演は親しみやすい作品だったと思います。そこに含まれる就職、非モテ、そして同性愛をギャグにする(そして客席も実際に笑っている)、その全てが既視感を持ち、普段の生活の中に溶け込んだワンシーンであるという発見が痛々しく、初々しかったです。
- 岡山大学演劇部「山田次郎物語」
「山田次郎」という架空の人物を想像してその誕生から描いていくという壮大な仕掛け(それは複数の役者が群舞的な躍動を伴いながら演じる)に対して、目の前で展開される「山田次郎」の存在感の希薄さが否めません。1人の人間の人生が抱えるエピソードは平均的寿命から考えてほぼ無限に等しいバリエーションで様々な出来事が起こるのではないかと思います。そうした中で今作の中で提示されていた「山田次郎」の人生の各場面の既視感が「山田次郎」を平面的で、存在の希薄な人物にさせていたのではないでしょうか。もしかすれば「山田次郎」という人物と観客の中に共通するエピソードを見つけさせることが目的だったのかもしれませんが、どの話もあまりにも単純化され、交わされる会話が「ぽさ」のようなものを追求するあまり、題名にもなっている「山田次郎」その人に興味を持つことができませんでした。
ところで邦楽の音楽をかけ、オープニング、ダンス、既視感のある話題、というのはアニメによくみられる一種「形式」だと言えなくもないのではないでしょうか?言い換えるなら「お約束」です。その中でもそれぞれのアニメには特色があり(アンチなどに)「アニメなんてみんな一緒じゃん?」みたいな失礼なことを言われても、毅然と言い返せるような魅力が詰まっていると思います。ただ中には「まあ確かに強く影響は受けているかな…」と答えに窮する作品も、きっとあるでしょう。そうした中でも「このエピソードは!」という様な魅力的な話を1つ持つだけで印象は変わり、そこから新しい物語も生まれるかもしれません。
話がそれましたが、1度きりの上演に留まらず、再演を繰り返す中で新しい物語の発展を期待する、そんな淡い期待を持たずにはいられない魅力的な作品と団体だと思います。
- 幻灯劇場「DADA」
幻灯劇場の「DADA」は個人的にあまり面白いと思えませんでした。45分間という時間、舞台を注視することができる充実は確かに存在していました。個別の役者の技量(中でも作劇の藤井君、鳩川七海さんは素晴らしいことは言うまでもないです)もあり、程度の差はあれ熱量を伴った役者が躍動するオープニングはその才能を決定づける演劇祭屈指の美しい情景でした。
ただ、頂けなかったのは単純に話がよく分からなったと言うことでした。「よくわからない」というよりほとんど「崩壊」に近いような気もしていました。いくつかのレイヤーが交差していたように思いますが、それぞれが群像劇として上手く機能しているとも感じられず、かえって混乱をきたしているように思いました。幻灯劇場は(僕自身過去の作品を観劇して―僭越ながら―指摘してきたことですが)長らく野田秀樹との作風の比較の中で語られることが多かったように思います。今作はそのような影は以前より後退し、より作劇の藤井君のやりたいことが(ミュージカルであること、ちりばめられたジョーク等からも)如実に表れているように感じら、真摯だなと思いました。それは「演劇人・藤井」の素顔が現れ、その分「粗さ」の様な部分も出てきているのだと思います。ただ今回は「その粗さ」がほとんど邪魔なレベルで出てきていたのではないでしょうか。
残念ながら1度しか拝見していないですし、戯曲に目を通したわけではないので実際のところはわかりません。しかしながら「物語」としてこれを云々と言うのはやはり(初見だけ)では無理がありました。それは戯曲だけでなく、役者の台詞回しだったり、技術的な問題だったり、その他の問題があったのかもしれません。もしかすると物語的なものは諸要素であり、単純に役者の躍動や音楽がこの公演の主眼だったのかもしれません。ではなぜこのようなことを言うのかというと、ラストの一連のシーンは確実に物語ありきでの美しさがあってこそのシーンだったのではないでしょうか?構図や、音楽だけではない軸があるからこそ決まってくる瞬間に(少なくとも僕には)物語が追い付いていないと思います。これまでの幻灯劇場の作品では45分の中でもその現実的な時間以上の想像力を喚起させる取り組みがなされてきたと思います。しかし、どうにも今作では今までの作品の様な印象を持つことができませんでした。
一体何故でしょうか?それは学生演劇で散見される「宗教」「性」「想像妊娠」(想像妊娠がこれほど頻出の題材として扱われるのは一体何故なのでしょうか?)といったある意味「学生演劇」(ないし学生の造る創作)に特有の頻出のテーマを扱っていることが(もしかすれば)関係しているのではないでしょうか?技術やテクニカルな部分では明らかに学生との一線を感じさせてはいながらも、主題がどこまでも「学生的」であり、凡庸なことが気がかりでなりませんでした。作家が本来的にこの題材に興味があって物語を紡いでいるのでしょうか? それは形式的に題材を借用するのではなく、そこから個別の物語の扉を(それこそロッカーの扉のように)開く意思があったのでしょうか?
あくまでも個人的に、私の眼前のロッカーは終始閉ざされたままでした。