レビュー
- 第9回 – 2024年
- 第8回 – 2023年
- 第7回 – 2022年
- 第6回 – 2021年
- 第5回 – 2020年
- 第4回 – 2019年
- 第3回 – 2018年
- 第2回 – 2017年
- 第1回 – 2016年
- 第0回 – 2015年
審査員講評 田辺剛 氏
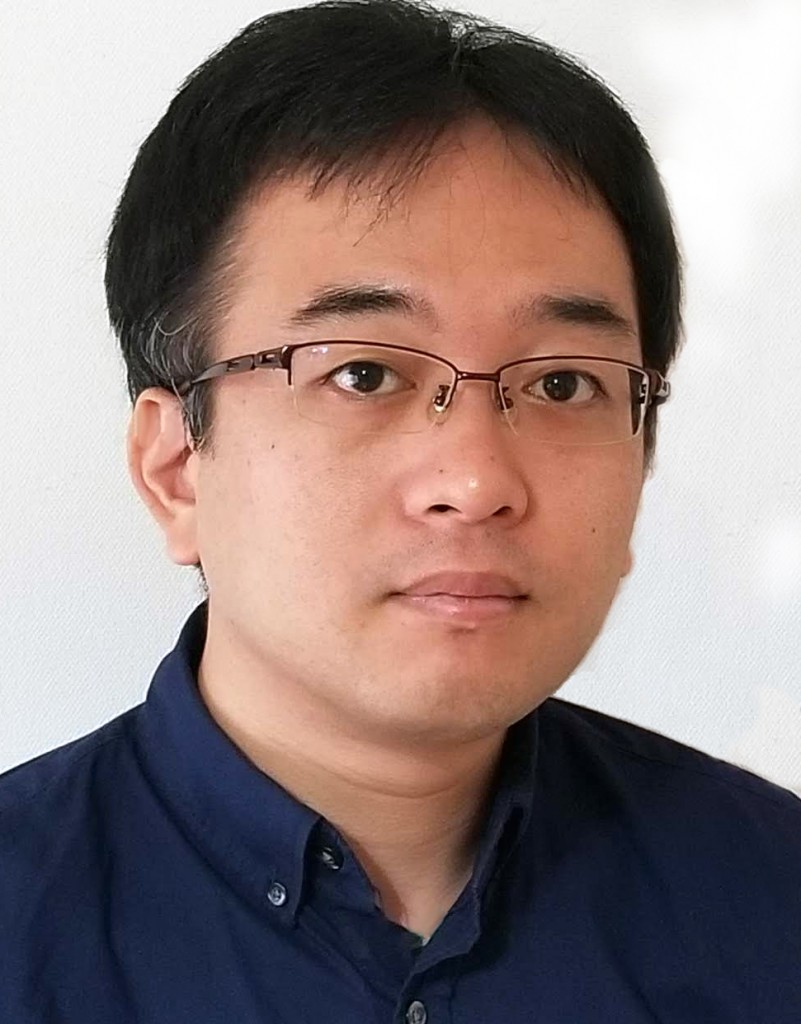
総評
選考会の場で審査員賞を授賞するにふさわしいとわたしが推したのは、青コン企画(仮)の『贋作E.T. の墓』だった。同賞には授賞の枠が三つあるけれどわたしはこの一作だけで十分だと考えた。同作はそのテキスト(戯曲)、演出、俳優のパフォーマンスのいずれに着目してもそれらの完成度は他の作品と比較して群を抜いており、確かにあら探しをすればいろいろ出てくるだろうけど、ここまでのものを作ったのが20代前半の若者たちであることを思い出して今後の活躍を想像すれば軽くめまいすら覚える。他の審査員が推さなかったことが不思議なくらいだ。同賞に選ばれたもう一つの作品、ギムレットには早すぎるの『らぴっど・ふらっと・ぷらっとほーむ』はわたし以外の審査員お三方がともに授賞対象に挙げられた。三人もが推挙するのだからわたしには気づけなかった魅力があるのだろうと反対はしなかった。その他にわたしの印象に残ったのは23Hzの『アンビバレンス』とどろぶねの『ノアの泥船』だった。
三つの授賞枠のうち一つが残って、これを埋めるか埋めないかということが議論になった。賞という肩書きを得ることが若い人の励みになるならばできるだけ出した方がいいという審査員の同意はあったがどの作品にするかがまとまらない。問題は、審査員賞に選ばれた二作品と同等に評価されるに値するのかということで、けれども候補として挙がった作品、劇団焚火『いけないらしい』、どろぶね『ノアの泥船』、そして23Hz『アンビバレンス』のいずれも先に決まった二作に比べると何かもう一つ二つ届かないものがあるというのも審査員の皆が同意するところだった。すると過去には既定のもの以外に賞が設けられたこともあるという事務局の説明があり、今回もそうして構わないということだったので「審査員奨励賞」というものを急きょこしらえたという次第だ。わたしは『アンビバレンス』を候補に挙げたが同作を挙げたのはわたしだけで、『いけないらしい』もお一人、『ノアの泥船』を挙げられた方はお二人。『ノアの泥船』はわたしとしても印象深い作品であるので授賞に賛成をしたのだった。
一人芝居や二人芝居が多かった。劇団の事情もあってのことかもしれないけれど、一人きりの舞台、あるいは二人しかいない舞台というのは、戯曲や演出そして俳優の演技にも三人以上出てくる作品と比べて特殊な作法があるだろうとわたしは考える。ザックリ言えば「もうちょっと人が出て来た方がいいんじゃないか」に負けがちだ。その余計なアドバイスに打ち勝つだけの作品としての説得力、あるいはそういうことが問題にならないような仕掛けが必要で、なんなら「むしろ一人で(二人で)良かったね」というくらいであって欲しいが今回拝見した作品には残念ながらそこまでのものはなかった。
幕切れで舞台が無人になるという作品がいくつもあった。つまり劇が終わると舞台が空っぽになり場内アナウンスが「終演です」と告げることでパラパラと拍手が起き始めるような事態だ。無人で舞台が終わることによって観客が最後に観るのはたった今まで誰かがいた、物語が紡がれていた空間そのものである。それまで人がいたせいで背景になっていた物語としての場所、あるいは人がいないことで空虚になったということ、それらを作品の核心として強く提示しようとする演出だが、果たして今回拝見した作品がそうした発想をもって(あるいはわたしが挙げた以外の視点でももちろん構わない)そうなっていたかと言えば心許ない。
作品を創作するときに冷静な第三者の視点が必要なのは言うまでもないことだが、作品への、または公演への思いが強ければ強いほどにその役割は強くなるように思う。信頼できるスタッフや先輩など周りもうまく巻き込めていくとより成果が出たのではと惜しく思われる作品がいくつもあった。
A-1 劇団焚火「いけないらしい」
虚勢というか、結局ウソだったと分かる男の現在の自己紹介が、時間を遡っていくやり方でどのようにして成り立ったのかが語られる。それがだんだんと虚勢(ウソ)だと分かる仕掛け、また幼少期から大人に至るまで、本人の成長とともに自己の内なる声、それは自己弁護の声だが、それがささやき程度の大きさからだんだんと本人と対等な音量にまで変化(成長)していく仕掛け、さらに空間を適切に埋める舞台装置や小道具類など随所に工夫がされていることは特筆されるべきだ。そのように語られ方には工夫があるけれども、語られる内容については男の半生が「幼い頃からなにかとうまくいかず他人のせいにしてきた」という紋切り型の域を越えてこない。幼少期から現在までを網羅して語ろうとするとどうしてもダイジェストのように浅く広くになってしまう。例えば語る時代に濃淡をつけるだとか、エピソードが観客に笑われる(笑わせる)文体であるとか、テキストレベルでの工夫があればよいのではないか。またほとんど全編にわたって演技がBGMに支えられているのも一人だけの身体で舞台空間と物語を支えられていないことの証左であるように思われたのも惜しかった。一人芝居は難しい。
A-2 劇団ちゃこーる「演撃所」
他団体を圧倒するようなエネルギーで全編を駆け抜けていった。その疾走を支える動機がもちろんあるはずなのだがそれを掴むのはわたしには難しかった。ここは海だと俳優が舞台で言えばそこは海になるというのが演劇だとわたしは先輩に教わり今でもそれを信じているが、この作品でもその演劇の原理は存分に使われていた。果たして場面はコロコロと変わるが、時折「いまはxページ」と告げる台詞があってそのページ数は進んでいる。たしか冒頭に台本を書こうとしているという描写があった。支離滅裂に場面が変わるように見えて一貫したなにか(台本の執筆)は進行しているようだ。その台本がこの劇なのか。友人を探しに行こうとしたが結局探すのはやめたのか。さまざまな題材が次々に出てくるが(メタ的なものがあって複雑さもある)それが出されっぱなしで終わっている。もしかするとカードをまき散らすようにしてみたかっただけかもしれない。けれどもそのまき散らされたカードを眺めるなかで浮かび上がるイメージがわたしにはなかった。散らかっているだけのように見えた。パンフレットなどを拝見すると演劇が好きだという一点で突破しようとしているようにも思われる。そうだとすればわたしも客席にいる人も程度の差はあれ演劇に関心がある人なのだから、そこへ向かって演劇への愛を説かれるだけではとも思う。
A-3 劇団蒼血「せんこう、消ゆる時」
写実的なリアリズムの物語では、曰く言い難いことを語るためにもはっきりと語れるものはおろそかにされてはいけない。本作品では「亡くなった高校の恩師の遺体が安置された自宅にどうして当の高校生だけがいて、彼らの登場から退場まで他の人が誰も見当たらないのか」という物語の初期設定が十分になされていないので、その後でどんな展開になろうがどんなことが語られようが観客としてはなかなかに受け取りが難しくなってしまう。俳優の声が聞き取りづらいのももったいなかった。ふだん稽古している場所から劇場へと移ったとき、たいていは広くなることになるが、俳優の声の響きを俳優本人と演出家によって検証して、例えば発声の仕方を変えるとか舞台装置の配置で反響をつくるなど、きっと認識はされていたと思うがその対処・調整がもっと綿密にされると良かったと思う。
B-1 どろぶね「ノアの泥船」
いまにして思えばこのタイトルにもっと注目をするべきだったと反省するのだが、というのも、日付変わって当日に体育の授業でダンスを発表しなければならない女子大生が深夜に一人きりで振付の練習をしているという物語の設定が興味深く、その夜をどう乗り越えて朝を迎えるのだろうかと期待が膨らんでしまったからだ。タイトルが示す内容よりもその物語の設定から生まれる展開に気が行ってしまった。たしかにそのタイトルがまずあって、冒頭では生き残った者への自撮りビデオの場面もあるのだからダンスの振付よりも大きな事態が別にあることが想定されはするけれども、コミカルかつリズミカルに進む振付の練習の描写がやはり目を引いた。ちなみに演出の問題として、ダンス音楽を劇場スピーカーから出すばかりではなくスマホから出すなどどこからの音なのかが意識されるとよかったとは思う。それにしてもミサイルが飛んでくる警報が鳴って練習が中断させられることには素朴に残念に思ったし、劇の結末が書けなくてそういうことにしたのかと邪推すらした。けれどもミサイルが飛んできて(作者によると必ずしもミサイルである必要はないという)、自身と自身が住む地域がもろとも壊滅的な破壊にあって命も落とすという状況が物語の根幹なのだと伺ってわたしはことばを失ってしまった。そうであれば劇全体の構成がそもそも間違っているということになるのではなかろうか。どうしたって「深夜必死に振付を覚えようとするお姉さん」の行く末が気になるように描かれているのだから。
B-2 青コン企画(仮)「贋作E.T. の墓」
ファミコンという昭和のゲーム機のカセットのような墓標を大地に差し込むことから舞台は始まった。亡くなった者を地中に埋めるパフォーマンスは人類に埋葬という文化が現れたことを告げる。墓標を前に墓を守る者と荒らす者の対立がある。時には暴力、時には卑猥なやり取りがリズミカルに展開してその舞台は墓穴の底にもなり巨大な墓標の上にもなる。劇空間をことばや身体のベクトルは縦横無尽に飛び交い、その軌跡はつねに観客の想像のなかに刻み込まれる。だから観ていて楽しい。メインの物語は映画『E.T.』をなぞったモノにも見えるが、宇宙人が出てくるまでに劇世界の初期設定は確かに済んでいるので劇の芯がブレることはない。墓標、墓守、墓荒らし、宇宙人、NASAとあらゆる題材にこの戯曲の作家が見る現在が反映している。一般に、複雑な世界はそうであるのに単純な二項対立の構図に収められることで制度化される。制度化はもちろん圧倒的な暴力がなせる技だ。構図が決まればそのなかでの争いも平和も把握可能なものとなるだろう。しかし時折その構図を破綻させるモノやコトが現れる。安定した構図が綻びをみせれば制度化の暴力は目を覚ましてその破綻の原因を潰しにかかるだろう。そうした事態を、確かに古典的かもしれないが、それを新鮮な手つきで物語世界として描いてみせた。そんな戯曲をもとに緻密に組み立てられたステージングを俳優はエルネギーを切らすことなくやりきった。戯曲の魅力をできうる限りの方法と尽力で引き出していたのではないか。もちろん細かなことを言えばいろいろ出てくるだろう。例えば劇を進めるリズムがせっかくあるのに転換でいちいち明かりを落とすのは興ざめだ。けれどもそうした細かなことがあってもなおこの作品の魅力は弱くならない。これからの創作のためにすべての指摘を飲み込んでもらえたらと思う。最後に、少年が宇宙人(E.T.)と墓標のてっぺんに上って自分が住む町やその先の砂漠まで見渡しているときの台詞を紹介したい。
少年 しかしこうも見えすぎると変な気になってくる。地面にいた時は気が付かなかったこと、記憶の町と俯瞰の町がまるで違って見える。昔はもっとごちゃごちゃしていたと思ったのに、いつからこんなに綺麗に真っ平になったんだろう、まるで(中略)お墓だ。
世界は刻々と姿を変えている。その変化に気づくのは実は容易ではない。気がついたときにはすでに変わった後だし、その時点で変化はさらに進んでいる。綺麗に見えるところも墓のようであるし暴力の場にはそれこそ本当の墓が溢れている。現在に上演されてしかるべき作品だった。この作品と出会えて幸せだった。
B-3 ギムレットには早すぎる「らぴっど・ふらっと・ぷらっとほーむ」
速いという意の”rapid”、平坦なという意の”flat”、そして駅の乗降口あるいは舞台そのものを指す”platform”。この作品のタイトルがどこまでを示しているのかは当団体に確かめるほかないが、これらの単語がひらがなになることで記号化されるとその意味は跡形としてのものになり、さらに中黒の点で結ばれることによってそれぞれの単語は並列に置かれるということ、このことが作品を象徴すると考えればわたしとしては腑に落ちる。コントのオムニバスのように断片的なやり取りが数珠つなぎに展開されいわゆる不条理劇のように見えなくもないが、それにしては物語の芯が分からない。冒頭の面接の練習をする場面でお笑い芸人になりたいという男が物語の主軸になりラストでは果たしてその男が漫才を披露することにもなるので、その男が冒頭で語った夢が主流になるのかとも思ったけれど、冒頭とラストの(劇のほとんどを占める)あいだがわたしのなかでは繋がらなかった。そこでタイトルに立ち返ってみればそもそもこの作品は一つの物語ではないとの宣言にも見える。意味だの物語だのは跡形くらいのものでしかなく記号化されて平坦に並べられた断片が矢継ぎ早に過ぎていく。舞台を凝視することなく椅子に腰を浅くかけて俯瞰するように見ていればいいのかもしれない。そのことがタイトルによってすでに語られていると考えれば腑に落ちる。とはいえしかし、と今でもわたしは考えあぐねている。
C-1 23Hz「アンビバレンス」
たいした脈絡もなく登場人物たちがそれぞれの秘めた本心を語り出すような作品を「告白大会演劇」とわたしは呼んでいるが、たしかに告白された心情に近いものを持つ観客には切実なことばとして受け取られもするだろうが、たいていは客席に座っているわたしとは関係がない。熱く語られたところで「みんないろいろ悩みはありますよね」としか言いようがない。つまり、ある人個人の思いや心情が演劇として披露されるときには、熱く語るだけではなく、さまざまな観客に共有される手立てが必要ではなかろうか。例えば語られる台詞がほとんど詩のような響きを持つだとか劇としてはコメディになっているとか、その語られ方に手立てがあることでその内容からは遠い観客もその場に居合わせることができるし、うまくいけば内容も共有されるのではないかと思う。
この作品の戯曲を拝読したときには典型的な「告白大会演劇」だと思ってずいぶん期待値が下がってしまったのだがその舞台にはとても驚いた。線路のように舞台に敷かれたLEDライトを使った空間の仕分け、小刻みに場面が変わるのを音によって告げるルール、地明かりはあったろうか、照明が空間を切り取る仕方もいさぎよかった。その二人の語りの見せ方が綿密に検討されているのがよく分かり、もちろんそれは戯曲を読んだだけでは分かるはずもなく、それゆえに驚いたしとても好感を持った。惜しむらくは俳優の身体に対しての演出だ。光や音響でもってあれだけの空間を創出したのに俳優の身体は台詞を語ることに徹せられているように見えた。冒頭の一瞬のダンスのような動きからパフォーマンス色の強いステージングになるのかと期待したけれど、音によって場面が変わっても身体に変化は見えず立ち尽くしているように見えた。声色には多少の変化があったかもしれないがむしろそれは不要だろう。そして光や音のルールが分かってくると注目されるのが舞台にいる二人の物語なのだけれど、自身の悩みに真っ直ぐすぎて、つまりこれも紋切り型の域を越えていない。俳優の身体やテキストがあの綿密につくられた光や音響の中に行儀良く収まっているのが歯がゆかった。もっとはみ出してほしかった。
C-2 劇団さいおうば「アキスなヨシオ」
物語の初期設定ということを先述したけれど、この作品もそこにかかっていた。つまり、空き巣と空き巣に入られた住人が出会ってしまうところから始まり、けれどもその二人が個人的な頼み事を「依頼する/引き受ける」関係になるにはいくつものステップがあるはずで、それを飛ばしては元も子もないということだ。本当は空き巣なのに新しい恋人のフリを「する/させる」のには二人の信頼関係が必要だが、それを築くためには相当な作業がさらに必要でそれなしにどんな面白おかしい展開になっても観客は置いてけぼりを食らうだけである。わたしはそうだった。また若い女性が一人で暮らすマンションの室内が舞台だが、上演する劇場の舞台が広いので物語の空間がどこからどこまでなのか明確に分かるようにされると見やすくなったかと思う。
C-3 劇団ど鍋「林檎をあなたに」
生きる確かさが感じられずあたかも人形のように生きている二人が共鳴しているのだろうと見て取った。今回拝見した作品のなかでも最も抽象度が高いように思われるのは舞台がことばのやり取りに特化されすぎているからだ。例えば二人を取り巻く環境や二人はいま何をしているところなのかということが台詞で語られることはあっても身体や空間に及んでいかない。登場人物に言わせたいことを劇作家は書き俳優はそれをいかに語るかに腐心している。それゆえ先述したように、そこで語られる内容が他人事ではないような観客には真っすぐ届くだろうがそうでない人には関わりがないだけになる。それが目的ならばある程度成功しているとも言える。けれども「届く人にさえ届けばいい」もそれを徹底していけば届かないはずの人を巻き込むことだってできるはずだ。その徹底していくプロセスこそが演劇なのではなかろうか。
田辺剛 氏 プロフィール
劇作家・演出家。劇団「下鴨車窓」代表。1975年生まれ、福岡県福岡市出身。現在は京都を拠点に創作、公演は全国各地で行っている。2005年『その赤い点は血だ』で第11回劇作家協会新人戯曲賞、2007年『旅行者』で第14回OMS戯曲賞佳作をそれぞれ受賞、2006年文化庁新進芸術家海外留学制度にて韓国に一年間滞在し劇作家として研修した。近年は子ども向けの演劇作品も手がけ、『きみがしらないひみつの三人』は令和元年度児童福祉文化財の特別推薦作品に選出された。また戯曲を執筆する講座の講師を数多く務め受講生から戯曲賞の最終候補者や受賞者も輩出し注目されている。